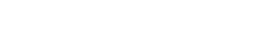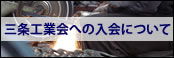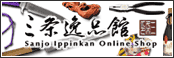- 研修期間
- 2024年9月~2025年2月
- 会場
- 三条鍛冶道場
ご指導をいただいた講師
- 日野浦刃物工房 日野浦 司氏
- 増田切出工場 増田 健氏
刃物製作のための鍛造・鋼付け・焼入れ・刃付けの技術習得
-
 ㈱坂源 大箭 敏史
㈱坂源 大箭 敏史今回初めて参加しました。
材料から刃物になるまで、多数の工程があり驚きました。
包丁を作るのは初めてだったので、すごく難しかったです。
中でも、鋼付けが一番難しく、なかなかくっついてくれませんでした。
講師の方々の助けもあり、なんとか完成させることができました。
大変でもあり、楽しい講習会でした。
ありがとうございました。 -
 下村工業㈱ 永井 孝宗
下村工業㈱ 永井 孝宗会社で行っている工程とは全く違った工程で包丁を作るということで四苦八苦しましたが、この経験を活かせる場面があれば活かしていきたいと思います。
-
 下村工業㈱ 垂石 治
下村工業㈱ 垂石 治初めて鍛造品に携わり、ものづくりの難しさを知ることができました。
材料製作や鍛造の温度管理が難しく、鋼が付かなかったり、横に伸びず薄くなったり、自分が思っている状態にならず苦労しました。
技術は一夜漬けでは身につかないことが分かり、今後の仕事でも意識しながら取り組みたいと思います。
講師の方々に助けていただきながら自分が作った包丁を作ることができました。
ご指導ありがとうございました。 -
 ㈱タダフサ 小山田 匡佑
㈱タダフサ 小山田 匡佑自分の会社で包丁を作るのとは全く異なり、会社では包丁に合った道具を作って工程通りにやれば作れるものも、鍛冶道場では包丁に合う道具を自分で考えていかねばならなかった。
火をおこすのに苦労して材料を赤くするのも時間がかかって、初心に戻って取り組め、マイスターのお二人に教えていただき、とても貴重な体験でした。 -
 ㈱タダフサ 伊勢亀 昂人
㈱タダフサ 伊勢亀 昂人今回初めて参加しました。
鍛接の時に目で見て温度を確認するのが難しくて、講師の方から何回も「まだ」と言われました。
そういったサポートもあり、初めてにしては上手く形にすることができました。
今回の研修で学んだことを今後の仕事にも活かしていきたいと思います。
ありがとうございました。 -
 ㈱タダフサ 浅原 龍太
㈱タダフサ 浅原 龍太今回初めて受講させていただきました。
始めは全く鋼を付けることができず、鍛接・鍛造の工程も理解できていない状態からのスタートでしたが、講師の方々からのご指導があり、受講回数を重ねるにあたり、工程の理解も深まり、私自身のスキルアップにも繋がることができました。
伝統工芸士の方々からの貴重な体験を受講させていただく機会をいただき厚くお礼申し上げます。 -
 新潟合成㈱ 福島 之広
新潟合成㈱ 福島 之広増田さん、日野浦さん、両氏に大変なご迷惑をおかけしながら、なんとか、形にすることができ、誠にありがとうございました。
昨年に引き続き、2度目の経験でありながら、覚えたはずの感覚は、単なる知識に過ぎず、何も残っていなかった。
という老体の悲哀を痛感しつつ過ごすだけかとも思うなかでも、自らの手が穿つ鉄の感触が、堪らなく思える瞬間。
本当に瞬間だけですが、これを日々感じられる方々は、やはり羨ましい。 -
 日野浦刃物工房 福迫 泰洋
日野浦刃物工房 福迫 泰洋現代の刃物作りは機械を使う工業的な仕事が多く手作業という物は少なくなってきました。工業会ではそんな時代に逆流する手作業のみという刃物作りをしています。
私は工場で毎日働いていますが手打ちのみで刃物を作る機会はまずありません。材料の叩き方・研ぎ方、様々なことを考えなければ刃物というものづくりはできません。いかに機械加工の便利さというものがよく分かります。
また、機械加工では決して分からないであろう使う人への気遣いや作る物へかける想いも今回の包丁作りで学んだ大切なことです。 -
 日野浦刃物工房 齋藤 一樹
日野浦刃物工房 齋藤 一樹「叩く意義」とは何か、その片鱗を感じることができた。
現代の生産現場においてコスト削減や大量生産が主体となり、ロボットやAIによる効率的なものづくりが蔓延する昨今、非効率かつ少量生産である伝統技術は何故近年まで生き続けるのか疑問に思っていた。
その中、日々の業務で集めた答えとなりうるピースが今回の鍛接によってハマる感覚があった。
「伝統」とは何か、「叩く意義」とは何か、改めて再考できる良い事業であった。 -
 皆川農器製造㈱ 皆川 基
皆川農器製造㈱ 皆川 基今回初めての参加で初めての包丁作りで、形にするのにとても苦労しました。
鋼を地金に付ける作業や焼入れ焼戻しなどが特に難しく、講師の方々にご指導いただいて何とか完成することができました。
大変な作業でしたが、進むにつれ楽しいと感じることができました。
良い経験になりました。ありがとうございました。